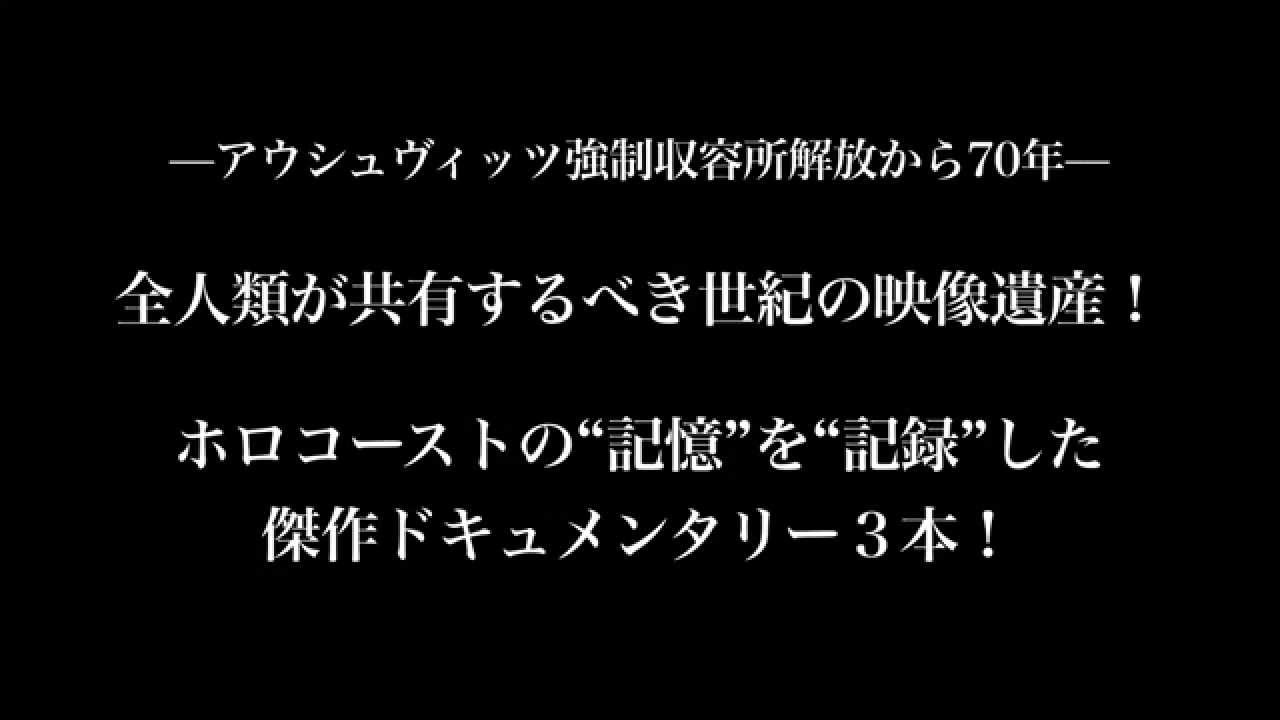
1970年代、ユダヤ系フランス人の映画作家クロード・ランズマンは、哲学者ジャン=ポール・サルトルらの支援を受け、20世紀人類のもっとも重要な体験のひとつであり、もっとも語るのが難しい事件のドキュメンタリー映画化に取り組んだ。ホロコーストと西欧の言語で呼ばれて来たこの事件は、ユダヤ人の言葉ヘブライ語では『SHOAH ショア』と呼ばれる。その言葉を題名として12年をかけて完成した映画は、以来少なくともフランス語圏では加害者側の呼称である「ホロコースト」よりも被害者側の言語による呼称で「ショア」と、今は呼ばれることが多い、その大きな理由となっている。
合計9時間27分に及ぶホロコースト体験の記憶の記録
第一部、第二部それぞれ4時間を越える合計9時間超の大作は、映画宣伝的には「ホロコーストの全てを語るためにこれだけの時間をかけた決定版」と言ってしまいがちだが、そう言ってしまった瞬間、映画『ショア』の本質は見逃されてしまうように思える。むしろこの9時間を見る、というより「体感する」経験から浮かび上がる、これだけの上映時間が必要だった真の理由は、ショアとヘブライ語で呼ばれる事件が決して語り尽くせないどころか、根本的に語り得ない、芸術表現に昇華させることで分かち合うことが可能な体験ではないという痛切な自覚であり、それは同時に、当時の記録映像などをふんだんに使うか、劇映画としての再現で「ナチスはこんなことをやった」を伝えることを投企としたいわゆる「ホロコースト映画」が、多くを見せているように見えて、実はなにも伝えていなかったし見せてもいなかったことを炙り出す。
我々が『ショア』で見るアウシュヴィッツやビルケナウ、ダッハウなどの絶滅収容所…ではなく、あくまで絶滅収容所の“跡/痕”は、かつて恐るべき残虐がその場にあったことの亡霊を秘めた風景ではあっても、それ自体はただの廃墟だったり廃屋だ。ユダヤ人を強制移送するのに使われた線路に、約30年後の現代(この映画の撮影時)に同じような蒸気機関車が行き来していても、その映像自体が伝えているのは「この鉄道はかつてこんなひどいことに利用されたが、今でも鉄道として機能している」であり、暴虐とあまたの死の歴史は映像には決して写らない亡霊として、手に届きそうで決して届かない領域に潜んでいる。
合計8時間ぶんには及ぶであろう証言は、ひとつの大きな物語としての全体像を構築するように撮られてはいないし、そう狙った編集も構成もない。我々がこの映画で接するのは主に生存者の体験談だが、それだけでなく現代から全体像を俯瞰しようとする歴史学者たちや、傍観者(実は加担者)であった普通のヨーロッパの市民、そして秘密裏に撮影が敢行された加害者側すら含む、膨大な人、人、人それぞれの言葉を、凡俗な教養主義的ドキュメンタリーにありがちな、ひとつのメッセージ性に収斂させようとする演出をランズマンはやっていないし、かといってより高度な映画表現としてよくある、観客が自由に自分の思考をめぐらし結論に達するよう促すことも、恐らくは最初から「不可能なこと」と自覚されている。
語り得ぬ体験/記録としてのホロコーストの本質に迫る
これは映画として恐ろしく難しい挑戦であり、ほとんど「反映画的」な試みでもある。観客に上映時間のあいだ映画を見続けさせるためには通常、ひとつの物語的な流れを構成することが不可欠だからだ。しかしクロード・ランズマンは、この題材でそんな「普通の映画」をやってはいけないことに、徹底的に自覚的だった。
『ショア』は社会的には、ホロコースト(ないしショア)についてのもっとも重要な映画作品として受け取られて来たが、映画史的にも極めて特異な存在であることを無視してはなるまい。「なにかを伝える」ことを狙っていないどころか、それを伝えること自体が不可能な題材に挑み、それは語り得ない、見せられないものなのだという本質それ自体を、いかに映画にするのか? 映画的であることを決定的に否定するよう運命づけられた題材を、その本質のまま受け入れることによってこそ、『ショア』は映画表現の核心に、限りなく近づく。
我々はしばしば映画の根源的なイノセンスを夢見て、映画史を意識して初期映画、例えばただ工場から出て来る労働者たちや駅に到着する列車の運動がキャメラの前に展開するだけで映画になっているかに見えるリュミエール兄弟による世界初の映画作品に、映画表現の純粋性を見いだそうとしたりする。だがもっとも「映画の根源的なイノセンス」が希求され、映画表現の純粋さにもっとも接近した作品は、実は映画が誕生して以降でもっとも忌むべき人類の所業を題材とした、この作品ではないだろうか? 9時間の上映時間は、映画が発明されたその直後には既に背負っていて、その後の映画史でどんどん蓄積されて来た、さまざまな「映画的」なる諸条件(たとえば2時間前後の上映時間、たとえばプロット構成)や夾雑物を、我々に忘れさせるためにこそ必要だったように思われる。
見せられない、そして語り得ぬことを、写せないからこその9時間から浮かび上がる映画の本質とはなにか?我々が理解し得ないほどの想像を絶する、しかし紛れもなく人間の行いであった歴史経験を証言するキャメラの前の他者たちに、同化を促すのでも共感するのでもなく、ただ見つめ続けること。その眼差しの強度こそが映画の本質であり、強いて言えば「愛」という言葉しか思いつかない。
愛と死をめぐるあらゆることがらは、善悪の彼岸にある
「愛をめぐることがらは、すべて善悪の彼岸にある」と言ったのはニーチェだが、愛の真逆にあるホロコースト、あるいはショアと呼ばれるこの事件もまた、安易な善悪の判断を拒絶するものとしてこそ理解されねばならない。「ナチスがこんな悪行をやった」と断罪するだけなら簡単だが、「ヨーロッパにおけるユダヤ人問題の最終的解決策」は、本当にナチス時代だけの特殊現象だったのか?
『ショア』を見ると、ナチスがこれを「ヨーロッパにおけるユダヤ人問題の最終的解決策」と呼んだことが論理的にはまったく正確であることを受け入れざるを得なくなる。ショア(ホロコースト)はただナチス・ドイツの蛮行であっただけでなく、文字通りヨーロッパ史を貫いて来た反ユダヤ主義、ユダヤ人差別が排外主義に至った近代に行きついた果てであって、ドイツだけを責めればいい、ナチスが悪魔だ、異常だったと言っていれば済むと思うのは欺瞞でしかない。9時間もある『ショア』に初見でまず圧倒され、二度、三度見るのはなかなか困難かも知れないが、それでも繰り返し見るうちに気づかざるを得ないのは、この明らかに途方もなく誤った、究極に犯罪的な出来事をめぐって、「人間的に正しい」「正義」の側にあると言える立場なぞなく、映画を作っている側もまた、その立場に立とうとも、提示しようともしてはいないだけでなく、それが不可能であることを自覚しつつ、むしろ映画キャメラの機械的記録装置としての人間的知覚感性からの独立性、あるいはただレンズを通して見つめるだけの、その映画映像本来の機能を受け入れている。
「いや、被害者の側に立つことが正義だ」と言い張りつつこの映画を見ようとする者もいるかも知れない。だがショア(ホロコースト)の現実の前に、被害者はただひたすら、人間であることすら奪われ、正しくあることも誤ることも、そのどちらの側にあることすら自らの意志では許されない立場にしか居られなかったのだ。それこそが600万人のユダヤ人を中心に一千万人以上がただ殺されただけでは済まない、この事件の根源的な邪悪さ、残酷さである。
『ショア』の19年後に明かされた、もうひとつの真実
だがランズマンがこの記念碑的な作品『ショア』を作り上げた時、そこにどうしても含めることが出来なかったもっとも力強い撮影素材があった、だからこそ作品から排除せざるを得ないでいたことが、21世紀になって明らかにされた。2001年、クロード・ランズマンは映画『ソビブル 1943年10月14日午後4時』を、『ショア』を作った当時の自分の限界の告白とともに発表した。
「あなたはそれ以前に人を殺したことがあるか?」「いいえ」、この謎めいてショッキングなやり取りから始まる映画は、唯一成功した強制収容所での叛乱についての映画…ではなく、当時16歳で叛乱の一員だったイェシェホア・レーナーの証言を中心に構成された作品であり、そのイェシェホア・レーナーという特別で例外的な個についての映画に徹することでこそ、ショア体験のある普遍的な真実を浮かび上がらせてもいる。
ソビブルはユダヤ人の叛乱が唯一成功した絶滅収容所であり、1943年10月14日とはその叛乱が決行された日付だ。『ショア』において人間性すら剥奪され、人としての主体性すら失い、入れ墨された数字だけがアイデンティティとされてしまったはずのユダヤ人たちが、自らの生存のために選択し、自らの意志で行動することに成功した、その証言であるこの映画は、『ショア』とは様々な意味で真反対の作品とも言える。
かつて大島渚が日本の戦争映画を「被害者しか描いていない」と批判したことは通常、政治的な意味合いで理解されがちだが、大島が言っていたのは有り体にいえば「だから日本の戦争映画はつまらない」ということでもある。つまり映画、とりわけフィクション映画とは、ある主人公(ないし主人公たち)が「なにかをした」、そのアクションを撮ることでこそ物語が構築され得るのに対し、受け身の被害者であり続ける主人公をただ見せ続けるのならそれは映画にならないし、そのまま映画にしたつもりでいるのなら、それはつまらない、つまり日本の戦争映画は「おもしろくない」という映画的な問題をこそ、大島は指摘していた。かと言って、ではホロコーストを巡って「なにかをした人間」が主人公とするのであれば、例えば「ユダヤ人を救ったオスカー・シンドラー」が主役の『シンドラーのリスト』があるが、果たしてスピルバーグのこの映画はホロコーストについて、本当はなにを語っていたのであろう?クロード・ランズマンはこのスピルバーグ作品を、表象できないことを表象したかのように装った映画だと厳しく批判している。『ソビブル、1943年10月14日午後4時』は、その表象/映画化不可能性の問題についての、彼の満を持しての回答でもある。
ドイツ兵を殺したことを、後悔はしていない
「あなたは人を殺したことがあるか?」「いいえ」。このやり取りはヘブライ語で、フランス語で質問するランズマンと通訳を介して行われる。そういえばイェシェホア・レーナーという名前もヘブライ語であり、つまり絶滅収容所で武装蜂起を起こし、脱走し、戦後パレスティナに行き、イスラエル国民になってからの名前であって、ソビブル収容所にいた時の彼の名前も、使っていた言葉も違ったはずだ。日焼けした精悍な顔の初老の男は、終始微笑んでいるが、その目が静かな悲しみをたたえていることを、クロースアップで凝視するキャメラは見逃しはしない。そして彼は淡々と、自らの収容体験と、秘密裏に行われた武装蜂起の計画、その実行を、ひたすら事実関係のみ、感情や感想を排して語る。
そのインタビューのあいだ、終始聞き手のランズマンは戸惑っている。
脱走の過程で、少年は自分と同年代であろうドイツ兵を殺害した。それ以前に人を殺したことはもちろんない。戦後イスラエル国民となっても、その国の戦争に反対し、参加せず、誰も殺していない。だがこの人生に一度の殺人を、彼は死んだドイツの少年兵には同情しつつ、それでも「後悔していない」と言う。かと言って復讐の欲望でも報復の正当化でもない。「なぜなら、私はその時、やっと人間に戻ることが出来たのだ」。
ホロコーストのもっとも本質的な残酷さとは、ただ600万のユダヤ人が殺されたことではない。人間であることを奪われ、尊厳どころか人としての主体性すら剥奪され、ただ入れ墨された囚人番号に還元されてしまった人格を取り戻すために、彼は自らの意志で、自らの生存のために殺人を決意し、実践した。だから後悔はしていない。
ランズマンは(このイェシェホア・レーナー氏の言葉をそこに組み込むことが出来なかった)『ショア』で絶賛されたあと、イスラエル国防空軍を撮ったドキュメンタリー映画を発表し、今度は「シオニストだ」と掌を返したかのような激しい批判を浴びたことがある。確かにホロコーストを生き延びたユダヤ人がイスラエル国家を建設し、その国民の生存の必然のためにアラブ人の国々と戦争をする(=殺人を犯す)という流れを(映画自体が必ずしもそう語っているわけではないにせよ)、イスラエルの戦争の正当化だと受け取られてしまえば、それはアラブ人、パレスティナ人の側から見れば簡単に許せることではない。そう誤解された点において、このイスラエル空軍の映画は確かに中途半端であった、とは言えるのかも知れない。
『ソビブル』を見ずに、『ショア SHOAH』は語れない
逆に言えば『ソビブル 1943年10月14日午後4時』を見ることで、『ショア』という記念碑的作品の本当の意味もまた、ここに初めて再定義されるだろう。あるアクションをなす主人公がいるという意味では「普通の映画」でもある一方で、その言葉にただ戸惑う作り手の震えた声が響き続けるこの作品の主体は、作り手ではなく単一の証言者の方にあり、逆に言えば複数の、膨大な数の証言者たちによって構成されているかに見えた『ショア』は、監督であり聞き手であるクロード・ランズマンが主体/主人公の映画であり、またそれ以外の構成はあり得なかった。
対照的に、『ソビブル』はイェシェホア・レーナーが主人公、彼の語りによって構成されている。そのレーナー氏の言葉と、微笑みを浮かべた顔に悲しみを静かにたたえつつ冷静な目に言葉を失ったランズマンは、それでも自分の声でこの映画をしめくくる。レーナー氏のように生き延びることが出来た者がいたのと同時に、あまたの死者も出したソビブル絶滅収容所の、その死者たちの名前と死因を読み上げる声だ。
死者たちの名をただ淡々と記すことは、ホロコースト犠牲者を追悼しその歴史を刻む多くの記念碑において、定例となっている表現法だ。だがそれを映画作家が自らの声でやっているようにも見えるこの映画のラストで、そこで読み上げられる無数の名のひとつひとつには、映画の文脈、レーナー氏の言葉によって一層の痛烈な響きが付与される。人格を奪われ番号に矮小化され殺された人たちについて、取り戻され得るのは名前だけで、それ以外のすべては、永久に奪われたままなのだ。
名前だけが遺された、膨大な死者たちのために
『ソビブル 1943年10月14日午後4時』はほとんどイェシュホア・レーナーの単一クロースアップの映画であり、その点でも『ショア』と対照的な作りになっている。証言のあいまあいまに挿入される現代のポーランドやイスラエルの風景は、『ショア』におけるそれ以上に、その風景、その場、空間の秘める歴史的記憶が、もはや現代の我々には手の届かないものであると同時に、しかしそれでも歴史の、生の、そしてもっとも悲惨な殺戮、人間であることそのものを奪われた上での死の、その亡霊が確かに痕跡を遺していることを示す。最後に画面が黒地に白い文字の連続となり、死者たちの名を読み上げるランズマンの声によって、映画そのものがあたかもトラックバックするかのように全体像を捉え、終わることは、無数の名が刻まれたホロコースト記念碑を前に我々が忘れがちな、ひとつひとつの名を読み識別することの大切さと、近づくと見えるが離れると見えない、つまり見えることと見えないことを巡る映画メディアの本質を浮かび上がらせると同時に、『ショア』が実はどういう映画だったかについて、最初にまず『ショア』を見終えた時とは異なった視点を、我々の内に喚起する。
膨大な死の記録だと思っていた『ショア』も、そこで証言する数多くのホロコースト体験者たちは運良く生き延びた人たちであり、その背後にはもはやなにも言うことの出来ないあまたの死者たちの、決して語られたこともなく、まして今後見ることなぞできない無数の、個々の体験があったはずであり、その証言、その人生は、永久に我々の知るところではないのだ。
辛うじて残されたのは膨大な名前や写真、その多くが彼ら一人一人がこんな運命に潰えるとは思っていなかったであろう頃に撮られた、まだヨーロッパのユダヤ人が人間であることを許されていた時の姿である。そのすべてが、名前さえも、彼らからは奪われたとき、人間であることを取り戻すための殺人を悔いよと、いったい誰がイェシェホア・レーナーに言えるのだろうか?では我々は彼を「許す」、あるいは受け入れ、擁護するのだろうか?映画のキャメラがアップで捉え続ける彼の顔そのものが、そんな次元を超越している。
監督が証言者に映画の主体をあえて譲り渡し、その事実上モノローグ映画の前にこれまでそれを映画にし得なかった自分の告白、最後に人間的主体性を取り戻すことなく亡くなっていった人たちの名を読み上げること、二つの自分の声のシークエンスをいわばブックエンドのような枠組みで構成した映画『ソビブル 1943年10月14日午後4時』に対し、さらに10余年を経て再び『ショア』の未使用撮影素材から作られた『不正義の果て』は、対話の映画だ。今回の証言者ベンヤミン・ムルメルシュタインは、ホロコースト生存者であり被害者であるはずの自分を「不正義な者たちの末端(原題のLe Dernier des injustes)」と呼ぶ。
イェシェホア・レーナーと同様、ムルメルシュタインもまたホロコーストのなかでただ人格を奪われ主体性を喪失した(そして命も奪われた)被害者であるままに留まらず、自らが「なにかをした」あるいは「やろうとした」、そのことで生き延びることが出来た主人公だ。彼は平然と言う、「ユダヤ人が殉教者になったのは確かだが、殉教者が聖人や善人であったわけではない」。
「ヒトラーがユダヤ人に贈った理想のゲットー」の真実
チェコ語の地名はテレジン、ドイツ語でテレズィエンシュタットは、ナチス政権下でのユダヤ人の扱いに対する国際的な疑惑や非難に対し、ヒトラー総統が自らユダヤ人に贈ったとされた「理想のゲットー」のプロパガンダ装置だった。表向きはユダヤ人の自治が行われていたはずであり、収容されたユダヤ人はユダヤ評議会とユダヤ長老の指導の下で理想的な環境で健全に働き生活していたはずで、ムルメルシュタインはその最後の長老だった(原題のLe Dernierは、時系列的な意味にとればこの「最後の」となる)。
むろん映画で真っ先に明かされるように、実態は他のユダヤ人収容所となんら変わりはなかった。そこに理想のゲットーを信じ、それなりに平穏な生活を期待して到着したユダヤ人たちが持参した財産が、まず駅で奪われた。現代のクロード・ランズマン自身がその駅のホームに立ち、歴史を説明し、ムルメルシュタインの著書の抜粋を読み上げ、テレズィエンシュタットのゲットーの跡を歩き、そこで密かに描かれた、記録の絵を紹介する。その美しくも陰惨で悲しい絵の姿で辛うじて遺された現実の光景は、死に取り憑かれた無惨で悲惨な強制収容所そのものであり、それがナチスが製作した「理想のゲットー」のドキュメンタリー映画抜粋と対比される。
「アイヒマンは悪の凡庸さなどではない、悪魔だった」
1938年にナチス・ドイツがオーストリアを併合して以来、ウィーンで若き有能なラビだったベンヤミン・ムルメルシュタインはユダヤ人社会の指導層の一員として、ナチス親衛隊の将校アドルフ・アイヒマンとも密接な関係で働くことになった。戦後イスラエル諜報機関モサドに逮捕されたアイヒマンの裁判と、その裁判を傍聴したハンナ・アーレントの報告『イェルサレムのアイヒマン』について、彼の批判は辛辣だ。命令に従った小役人としてアイヒマンを形容し「凡庸さの悪」を論じたアーレントに対し、彼はアイヒマンは凡庸な男などではなかった、悪魔だったと断言する。苛烈で痛烈なアーレント批判、ムルメルシュタインが目撃していたアイヒマンの罪状を立証しなかったイスラエル司法への批判も、このインタビューが『ショア』に含まれなかった理由のひとつなのかも知れない。
だがアーレントを批判しながらも、ムルメルシュタインも実は彼女と同じ論理を展開している。「組織化・効率化」を金科玉条として強圧的、横暴に彼らユダヤ人たちに接したアイヒマン、裁判では姑息な詭弁を弄し、ムルメルシュタイン本人が証言すれば立証できたはずの人道犯罪行為(たとえば「水晶の夜」で彼は直接指揮を執っていた)の幾つかで断罪を逃れたアイヒマンは、まさに凡庸な小役人そのものだし、だからこそ究極の悪の実行者なのだ。そしてムルメルシュタイン本人もまた、アーレントの言葉を借りれば「恐怖の体制」の下に、そこに屈服しながら生残りを模索したことは否定しようがない。だからこそ彼自身、戦前戦中のユダヤ人長老の最後の生存者である自分を、Le Dernier des injustes, 最後の不正義なる者、ないし不正義の体制の末端と呼ぶ。
ムルメルシュタインがユダヤ人コミュニティの指導層としてアイヒマンと渡り合う、いや結局は命令を受ける立場であったことから、その証言によって「ヨーロッパにおけるユダヤ人問題の最終的解決策」がどう計画され実践に移されて行ったのかのプロセスの実態が浮かび上がる。
「ユダヤ人問題」の解決とは、ユダヤ人がヨーロッパから居なくなること。その手段は問われない
ユダヤ人がヨーロッパにいること自体が問題とされ、故にユダヤ人をどこかに移住させようという発想から全てが始っていたことが、痛烈な皮肉としてユダヤ人側のある動きともある利害の一致を見せさえする。シオニズム、ユダヤ人国家建設運動は19世紀の末に南米案なども経つつ、結局は民族の故郷であるパレスティナに決まっていた。その一方で、ヨーロッパの側でもどこか別の土地にユダヤ人を送り出す意志が産まれていたのはナチス・ドイツに限ったことではなかった。
最終的にホロコースト直前に出た案として、マダガスカルという候補が、1939年9月、ドイツ軍がポーランドに侵攻し第二次大戦が始る直前に、ポーランド外相がベルリンを訪問してナチスに提案していたという、この今までほとんど知られていなかった驚愕の事実は、クロード・ランズマンによって語られる。
よりによってアフリカの西に浮かぶ島という発想が、反ユダヤ主義とヨーロッパの差別排外主義、そして植民地主義と密接かつ絶望的に結びついていたことを痛烈に示していて愕然とさせられるのだが、ところがそこでムルメルシュタインが登場し、我々が浸っている沈痛な衝撃をさらにひっくり返し、このとんでもない案ですら欺瞞に過ぎなかったことをあっさりと指摘するのだ。
ムルメルシュタインは言う、マダガスカルとはヨーロッパ人にとって自分たちの世界観の外の意味しか持たず、実現性なぞそもそも考慮されていなかったどころか、まったくの人間外の別世界、つまりは「死」をこそ意味していた。「ユダヤ人問題の最終解決策」としての民族絶滅計画は、この時にこそ始っていたのである。
群像劇、モノローグ、そして対話の映画
ランズマンがムルメルシュタインとインタビュー映像のなかで対話し続けているだけでなく、30余年を経て撮影された現代のランズマンが朗読し語ることもまた、1975年のローマで撮影されたムルメルシュタインの映像と対話の関係にあり、ランズマンが告げる事実関係から我々が想像しがちなこと、インタビュー当時のランズマン(と観客の我々)が思いつきそうなことをひっくり返しながらも、それは否定ではなく思考をより深化させるべく作用する。
『ショア』がモザイク的に構成された全体像、『ソビブル』がひとりの主人公の物語映画なら、『不正義の果て』は何重もの入れ子構造を持った、対話の映画なのだ。
ドイツのオーストリア併合、水晶の夜、第二次大戦の勃発、そして「ユダヤ人問題の最終解決策」に至る歴史において、ベンヤミン・ムルメルシュタインは被害者のユダヤ人であると同時にその立案プロセスの目撃者であり、加害者側組織の一員ですらあった。生存のためやむを得なかったのか、彼自身の責任ある判断だったのか、このランズマンの問いに、彼はあっけなく自分の主体的な意志だったことを明かす。たとえばアメリカの大学に招かれる話もあったのを断り、自らウィーンに残り、アイヒマンと共に働くことを選んだのだ。自分がその指導層にいたユダヤ人コミュニティのためなのか、自分の能力からして果たすべき役割があると思った自尊心なのか?彼は自分の当時の心理を、「若さからの冒険心」と形容する。
テレズィエンシュタットのゲットーから解放されてから30年後のローマで、キャメラの前のムルメルシュタインはあくまで饒舌だし、ハンナ・アーレントへの批判も、自分の前任者のユダヤ長老についての論評も、時にあまりに辛辣だ。一方のランズマンも、時に気兼ねのあまり訊ねにくいはずの問いですら、彼に投げかける(最初はフランス語で、通訳を介していたのが、途中からドイツ語でのやりとりになっていく)。
ムルメルシュタインの証言映像のあいまあいまに、現代のテレズィエンシュタットでランズマンがユダヤ人の処刑が行われた幾つかの場所に立つシーンが挿入される。そこで起こったことを語る映画作家は、時に感情の高ぶりを自らに禁じ得ない。だがそんな非業の最期を遂げたことが語られた先代の長老について、ムルメルシュタインがすかさず痛烈な批判を述べる。しかしムルメルシュタインのこの熱弁を感情的だと誤解したり、自己弁護のためと邪推することはできない。むしろ徹底して理路整然としている赤裸裸な内容の語り口は、話しっぷりの熱っぽさとは裏腹に、恐ろしく冷静でさえある。
そう、「ユダヤ人が殉教者になったのは確かだが、殉教者が聖人や善人であったわけではない」、むしろそうあり続けられたわけがないのだ。ホロコーストの体験とは善悪の彼岸にあり、ムルメルシュタインに限ったことでなく、そうしなければ生き延びることが出来なかった選択をした人たちも大勢いるはずだし、その選択を実行したからといって生き延びられた保証はない。ドイツ少年兵を殺すことで「私は人間に戻ることが出来た。だから後悔はしない」というイェシェホア・レーナー、そしてこの残酷なる「最終的解決策」を「最終」としないために積極的にその加害組織の一部であり続けたベンヤミン・ムルメルシュタインの生きた軌跡に、今さら自己正当化に務め善人を装おうとする意味なぞあるまい。『不正義の果て』を「一方的に過ぎてアンバランスだ」という評も出ているが、いったいその人々はどのような「バランス」を、ショア体験の証言に求めているのだろう?いったいどのような「正義」で、この自ら「最後の不正義なる者」にして「不正義の末端」を名乗るムルメルシュタインを、現代の我々が断罪できるのか?
ユダヤ人が殉教者になったのは確かだが、殉教者が聖人や善人であったわけではない
最年少の長老としてティエレズィンシュタット・ゲットーの衛生部門の統括を引き受け、先代の三代目長老が処刑されたあとはその全てに責任を負うことになったムルメルシュタインは、プロパガンダの欺瞞と知りながらあえて自分は「ヒトラーの理想のゲットー」の一部になったと語る。テレズィエンシュタットの虚構を維持する限り、このゲットーは存続だけは許されるはずだ。こうして彼は自ら、自分たちユダヤ人を絶滅させようとするシステムの一部にすらなることを厭わず、その組織内部の人間だからこそ出来る要求をナチス側に突きつけさえして、疫病を予防し、老人ホームを作り、ユダヤ人たちにはナチスの注文に応じた製品を生産する労働を義務づけさせさえした。働き続ける限りは殺されない、また自らの主体を完全に見失うこともないはずだと、実のところなんの確証もなくとも、それでも確信しなければ、生き延びることはできなかったのだ。こうして表面上は加害者に協力し奴隷の身に甘んずる決断すら、ユダヤ人たちにとっては壮絶な、自らの主体を賭けた戦いになる。
それでも些細な規則違反を理由に多くの者が処刑され(ムルメルシュタインが痛烈に批判する三代目の長老も含む)、若者たちが「東へ」移送されて行った。東、つまりアウシュヴィッツ=ビルケナウであり、そこから二度と出られない死を意味することはなぜかテレズィエンシュタットのユダヤ人たちの共通認識になっていたし、不衛生な状態でこのゲットーに到着した少年たちがまずシャワーを浴びることになった、その子どもたちは「毒ガスだ」とパニックに陥ったという話にランズマンは驚く。極秘で遂行されたはずの「最終的解決策」の最終段階でなにが行われたのか、多くのユダヤ人が既に知っていたのだ。ムルメルシュタインは自らが結果としてその立案に関与してしまった計画の行きつく果てを当時から知っていたことも隠さない。だがその「悪」ないし「不正義」の知は、だからこそテレズィエンシュタットのユダヤ人を出来る限りそこには移送させまいとする彼の動機にもなった。
善悪の彼岸
『ソビブル 1943年10月14日午後4時』と『不正義の果て』という二つの人間としての生存の必然の軌跡を見て、『ショア』に再び立ち戻る時、その9時間を越える体験は、まったく異なった様相を観客たる我々の前に現すだろう。映画としては9時間という膨大な長さとスケールを与えられていたとことで、ホロコーストを語り尽くすことなぞあり得ない。最初は9時間かけてこの歴史を学んだつもりになれたかも知れない者は、実はなにも分かっていなかったことに気づくだろう。ホロコーストそのものが、我々人類の歴史に刻印された見えない刻印、我々の世界に取り憑き続ける、決して語り得ず、理解しきれない亡霊なのだ。
『不正義の果て』のラストシーン、そして『ショア』に始ったクロード・ランズマンの三部作の最後の映像は、古代ローマ遺跡フォロ・ロマーノを仲良さそうに散策するムルメルシュタインとランズマンの姿だ。
ユダヤ人にとっては裏切り者であるムルメルシュタインのような人間は、ユダヤ人の手で処刑されるべきだ、という発言すら出ているイスラエルに、彼が足を踏み入れることはなく(アイヒマン裁判の証人として自分を召還しなかったイスラエル政府も、彼は辛辣に酷評する)、その彼がかつてユダヤ人の王国を滅ぼし、民族離散のきっかけとなったローマ帝国の遺跡を歩いていることは、考えてみれば悲痛な皮肉にもなっている。だがそんな自らの民族に降り掛かった命運を嘆くことなどまったくないこの生存者、ベンヤミン・ムルメルシュタインに、ランズマンが最後に言う、「あなたは虎だから」と。
インフォメーション
シアター・イメージフォーラム他にて公開中(配給:マーメイド・フィルム)
http://mermaidfilms.co.jp/70/
『ショア SHOAH』(1985年)
『ソビブル 1943年10月14日午後4時』(2001年)
『不正義の果て』(2013年)
監督:クロード・ランズマン
France10は広告収入に依らないタブーなき報道のために皆様からの御寄付を御願いしております。
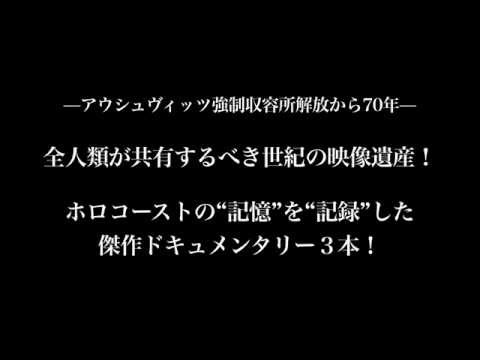

コメントを残す